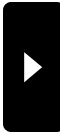2014年03月03日
働く介護者の会を開催しました。

3月2日、働く介護者の会を開催し、働きながら
在宅介護をしているお子さんが、介護を受けている
ご本人(親)と参加してくださいました。
その方とは、認知症の勉強会などで知り合った
のですが、個人的にわざわざ会ってお話した
ことがなかったので、ゆっくりお話しできました。
ご本人さんは、なぜここに来たのかも理解できて
いなかったのですが、私がお子さんとお友達だと
話をしている様子を見て、安心されたのか、
ウトウトとしておられました。
たつの市は、いろいろな研修をしているが、
ほとんどが平日の昼間に開催されていて、
働く介護者は参加したくてもできない。
その訴えが、印象的でした。
私たち支援者は、そうした家族さんの生の声から
課題を見つけ出し、改善していかなければ
ならないだろうと思っています。
来月は、4月6日(日)午後1時~3時に開きます。
ご参加されたい方は、お申し込みをお願い致します。
2014年02月04日
ケアメン☆サミットJAPANからのメッセージ
<私たちのメッセージ>
全国100万人の男性介護者に、
いま・ここに介護を生きる仲間として連帯のメッセージを送ります。
1. かたろう!男の介護
2. つたえよう!私の介護体験
3. ひろげよう!介護の仲間と集い
4. かえよう!介護保険と介護休業
5. なくそう!介護退職と介護事件
私たちは「介護の日」を記念し、この5つのスローガンを掲げて
「ケアメンサミットJAPAN」を開催しました。
介護によって仕事が断念され暮らしが破壊されることなく、
その両立を目指す取り組みを、私たちの重要なミッション(使命)と
確認しました。
「介護退職ゼロ」の雇用環境と、「介護する人・される人」を
社会で支える包括的な介護支援制度、の実現です。
介護される人の幸せも介護者の幸せも共に尊重
される社会でなければなりません。
今回の「ケアメンサミットJAPAN」をその第1歩として、
私たちのミッション(使命)を全国に広げていくことを宣言し、
〈私たちのメッセージ〉とします。
錦秋の京都から
2013年11月17日
男性介護者と支援者の全国ネットワーク
ケアメン☆サミットJAPAN参加者一同
全国100万人の男性介護者に、
いま・ここに介護を生きる仲間として連帯のメッセージを送ります。
1. かたろう!男の介護
2. つたえよう!私の介護体験
3. ひろげよう!介護の仲間と集い
4. かえよう!介護保険と介護休業
5. なくそう!介護退職と介護事件
私たちは「介護の日」を記念し、この5つのスローガンを掲げて
「ケアメンサミットJAPAN」を開催しました。
介護によって仕事が断念され暮らしが破壊されることなく、
その両立を目指す取り組みを、私たちの重要なミッション(使命)と
確認しました。
「介護退職ゼロ」の雇用環境と、「介護する人・される人」を
社会で支える包括的な介護支援制度、の実現です。
介護される人の幸せも介護者の幸せも共に尊重
される社会でなければなりません。
今回の「ケアメンサミットJAPAN」をその第1歩として、
私たちのミッション(使命)を全国に広げていくことを宣言し、
〈私たちのメッセージ〉とします。
錦秋の京都から
2013年11月17日
男性介護者と支援者の全国ネットワーク
ケアメン☆サミットJAPAN参加者一同
2014年01月31日
2月2日 働く介護者の会

龍野町で行います。
チラシの電話番号にご用件、電話番号を
残していただけましたら、1月31日、2月1日の
うちに、折り返しご連絡を差し上げます。
または、2月2日当日の12時30分以降に
お電話いただけましたら、場所をご説明
いたします。
2013年12月26日
働く介護者の会
2013年09月13日
加古川元気会に行って来ました!

今年度に入って、「たつの介護福祉ねっと.」が
発足したり、諸々の用事と重なったりして、
加古川の家族会に参加できませんでした。
このまま足が遠のいてはいけない!と先日、
久しぶりに行ってきました。
デイサービスに通っていたご主人が脳梗塞を
起こして入院、今は施設に入所したという
お話を聞いてびっくり。
若年性認知症の班には、新しい方が何人が
入られ、先輩の方が進行役になっていて
びっくり。
ほんの数か月の間に、いろいろな変化がありました。
前半のミニ講座の最中には、認知症のあるご本人が
ご家族と離れて、何ができるようにと、託児所ならぬ
宅老所ができていて、先日は、写真のような
作品を作られていました。
大きく育ってしまったオクラを切って、ハンコにし、
色とりどりの作品を作っていらっしゃいました。
元気会では、今、5周年に向けた文集作りも
行われていて、ご家族も家族会の中でしっかり
役割を果たされていらっしゃいました。
2012年01月06日
大スクープ!

昨年、静岡の富士市で始まった「介護マーク」の使用。
このブログでも紹介しました。
http://nintomo.tenkomori.tv/c8417.html
富士市は、行政を通じてデザインの使用を認めて
いたので、以前、たつの市にも提案をしました。
しかし、他地域の様子を鑑みて検討するという
反応でした。
あとはもう国にお願いするしかないと、厚労省にも
メールを出しました。
恐らく、全国各地から同様のお願いがあったのだと
思います。まもなく厚労省から自治体レベルで
この「介護マーク」の普及をすることを決定しました。
その動きは知っていたので、あとは市の動きを
待っていたのですが、今日、直接メールをいただき、
広報2月号で紹介し、配布を始めるということ。
やったー!
すぐには広まらないかもしれません。
でもこのマークによって介護を隠そうとする日本の風潮を
変えられる可能性がある。
私は介護中ですが、何か? と言える社会。
人間が長生きするのだから、「介護」という時間が、
されるにせよ、するにせよ、必ず訪れるのです。
だからそれが普通になってほしい。
普通だから、普通に手を差し伸べられるように
なったらいいと思うのです。
2011年09月22日
つどい場 安暖庭

ついに「つどい場 安暖庭」に行ってきました。
今日の午前中はインドネシア候補生の授業があり、
そこまでご主人が迎えにくてくださいました。
場所は前に確認していたので、高台にあることは
知っていましたが「つどい場」からは、台風が
過ぎた後の静かで青々とした海が一望できます。
私が到着したときは、もう会が始まっていて、
皆さん、自己紹介の最中でした。
介護をされるご家族の苦労はどなたも共通して
いるように思います。が、その受け止め方には
少しずつ違いがあるようにも感じました。
そして話始めたら止まらない(笑)
そりゃ、24時間体制の介護をずっと続けていらっしゃる
んですから、2,3分なんかで話が終わるはずは
ないですね。
友人や近所の人との会話が減ってきて、胸の奥に
ためている思いがいっぱいあるのでしょう。
「介護」という共通のテーマで皆さんが真剣に
話を聞いてくれるのですから、熱が入るのもよく
分かります。
だからこそ、このような「つどい場」や「家族会」
が求められているのだと思います。
自己紹介が済んだら、お楽しみのランチ♪
お庭でとれた栗を使った炊き込みご飯、天ぷら、
茶碗蒸し、それから・・・ あまりに美味しくて
写真を撮るのを忘れてしまいました。残念。
そして、集まった方々との雑談。
認知症とアルツハイマーの違いは何か?
そんな質問をされている方がいました。
世の中、まだまだ認知症の理解が不足している
んだな~と思った瞬間でした。
介護者にもっと認知症の知識があれば、認知症ケアが
変わるはずですが、知識がなければ、自己流の介護を
してしまう。
けれども、質問された方は無料の講演会や勉強会には
あまり関心がないようで、少し残念に感じました。
私たちが目にする、ご本人の行動は「症状」であり、
そこに至る「根拠」や「理由」が存在するのです。
熱があるからと、氷枕をすれば治るわけじゃない。
足が痛いからと、湿布をすれば治るわけじゃない。
なぜ熱が出るのか、なぜ足が痛いのかが分からなければ
治療の仕様がないのです。
それと同様に、認知症の中核症状やBPSD(周辺症状)が
なぜ出てくるのか、根本的な原因を探っていかなければ
適切な介護はできません。
学ぶことの意義がいつの日がご理解いただけることでしょう。
会の最後は、参加者の方のアコーディオンの演奏で、
皆で「赤とんぼ」「ふるさと」などを歌いました。
加古川の家族会でも歌を皆で歌いますし、私も職場で
利用者さんとよく歌を歌います。
大きな声で歌うと発散でき、いいですね。
また、一緒に行ってくださる人を探して、訪問させて
いただきたいと思いました。
2011年09月22日
思いがけず

前の記事のコメントで、アンダンテさんに
介護家族のつどい場に来ないかと誘っていただき、
今日、訪問させていただくことになりました。
それも送迎付きで!
大変ありがたいことです。
ずっと行きたかったのです。
社協の「つどい場」で行くときは、都合がつかな
かったり、予定を間違えたり、
車を出してくれる人が見つかった時は、
アンダンテさんが夏休みだったり、
なかなかご縁がなかった。
でも「咲咲館」や「つどい場さくらちゃん」では
アンダンテさんのことが話題にのぼって、全く
縁がないようでもない。
だからいつかきっとチャンスは訪れると思っていました。
そしたら急にお誘いが舞い込んで、とても嬉しいです♪
今晩、晩の11時過ぎに夜行列車で横浜に向かいます。
明日は「笑福会」の全国大会もあり、いいお土産話が
準備できそうです。
2011年08月17日
咲咲館→つどい場さくらちゃん

咲咲館の記念すべき第1号ランチ!
発泡酒で乾杯~♪
昨日は、もともと仕事のない日で、お盆休み
でもあったので、普段の予定もすべてお休み。
まずはネットサーフィンでも、とあちこちの
ブログを訪問していました。
8月7日の記事で紹介した「咲咲館」のブログに
http://nintomo.tenkomori.tv/e248174.html
行ってみると、先週の土曜日は来客がなかったと
書いてあって、管理人さんから一度遊びにきて
くださいとお誘いを受けていたことを思い出しました。
火曜日はオープンの日なので、今から出れば
ランチに間に合うかな?と慌てて仕度をして
西宮目指して出掛けました。
姫路からお電話を入れて、オープンを確認し、
11時すぎぐらいに咲咲館に到着しました。
そこはマンションの1室。明るい空間でした。
さっそく名刺交換をして、私のしている「はこべら」の
活動や笑福館の紹介をさせていただきました。
私ばかりが話をしてしまいましたが、こうして
支援者同士がつながることが大切だと思っています。
そこでも出た話ですが、こうした活動について
行政が広報などのサポートをしてくれると
もっともっと「救われる介護者」がいるはずだと
思うのですが、積極的な支援はありませんね~
それはさておき、男性介護者の方との繋がりが
広がるといいですね。
メッセージを発信し続けましょう!
そして咲咲館の代表の計らいで、あの「つどい場
さくらちゃん」も訪問することができました。

こちらは西宮の駅前。こんなところに家が!
みたいな場所にありました。
部屋いっぱいにダイニングテーブルが2つあり、
その周囲に椅子がぐるっとめぐらされています。
奥の人がトイレに行くのに、皆が立ちあがらないと
いけないぐらい、部屋いっぱい。
訪ねたとき、同時にお客さんがやってきて、
しばらく「まるちゃん(神)」とお話ができなかった
けれど、お客さんが帰ったあと、いろいろお話
させていただきました。
お疲れだろうな~と思いながらも、噂どおり
元気な「まるちゃん」で、私たちの活動についても
ヒントと勇気をいっぱいいただきました。
思い付きで行動した1日でしたが、とっても充実し
幸せな1日でした。
2011年08月07日
男の介護「咲咲館」オープン!

男の介護は特別じゃない
と、男性介護者の悩みを共有しようと
4日西宮に「咲咲館(さくさくかん)」が
オープンしました。
ホームページ http://sakusakukan.web.fc2.com/
ブログ http://sakusakukan.blog59.fc2.com/
加古川の家族会にも、ぼちぼち男性の介護者の
方も参加されていますが、そういうところに
参加できる方はまだいい。
妻や母親を介護するようになるまで、ご飯も
炊いたことはない、子供のおしめも替えたことの
ない男性が、意思疎通の難しい大人を相手にする
ことは本当にストレスだと思います。
虐待をする人のトップは「息子」です。そして
「配偶者」これはたぶん「夫」でしょう。
憎いとか、面白半分で虐待をするのではなく、
すべが分からず、怒りをぶつけてしまうのだと
思います。
だから、男性介護者の支援する動きがあちこちで
出来始めました。
咲咲館のオープンをきっかけに兵庫県内の「男性介護者支援
ネットワーク」ができたようです。
http://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/0004332510.shtml
近いうちに出かけてみたいと思います。
2011年05月25日
一通の手紙

昨日、帰宅すると、最近では珍しく個人からの
お手紙が届いていました。
認知症サポーターの研修で知り合った方で、
ご自身も介護家族の方です。
3月、ある集いで入院中のお婆さんを毎日看病している
話を伺いました。ずっと寝たきりになると身体の拘縮が
起こり、それを伸ばしているというお話でした。
以前、知り合いの理学療法士さんから、拘縮は伸ばす
だけではだめ、拘縮が起こるのには理由があり、
それを改善してあげることで身体が緩むというお話を
聞いたことがあり、私はその方の話を聞いてすぐ
理学療法士さんに相談しました。
拘縮は、重力に逆らって起きる
ベッドの上で体重を支えているのは背骨を
中心にした周辺の部分だから、丸みがあって
ベッドについていない部分にクッションなどを入れ、
体全体で体重を支えるようにすると身体は緩む。
そういう理屈です。
私は寝たきりの介護をしたことがないので、その
事実を目で確認したことがありませんが、理学療法士さんが
送ってくれた資料の写真では、同じ患者さんの
身体の緩み方が明らかに違います。
その資料を介護されているご家族の方に送りました。
送ったのは4月の初めごろだったと思います。
そして昨日の手紙。
手紙を送った頃、拘縮も強くなり、諦めかけていた
ときだったそうで、思いがけず資料が送られてきて、
何度も繰り返し読み、もう一度、拘縮を緩めるために
がんばろうと思い立った。そんな内容でした。
お婆さんは結局今月亡くなられたそうですが、
その手紙からは、納得のいく介護をしきったという
気持ちが感じられました。
状態にあった適切な介護技術をご家族に伝えていくこと。
それは専門職の役割でもあり、またそれに応えられるよう
技術、知識を向上させていかなければと、改めて
気持ちが引き締まりました。
2011年05月10日
災害と認知症

今日は加古川元気会の日。
ミニ講座の講師をさせていただきました。
資料は作ったものの、特に流れを決めておらず
ダラダラと私の思う「災害の備え」について
お話をさせていただきました。
特に「よかった」という感想もありませんでしたが(笑)
それでも「災害時要援護者」の登録について
知らなかった方がいたり、加古川で5000人を越える
認知症サポーターがいるにも関わらず、ご本人や
ご家族の周辺には具体的な支援者がいないことが
わかったり、まだまだ「備え」が不十分であることを
お伝えできたのではないかと思います。
認知症サポーターは「何か特別なことをする人ではない」
と説明がありますが、統計資料には、その地域の
「高齢者の人数に対するサポーター数」が出ているわけで、
やはり今後、社会資源としての支援者をしっかり
確保していく必要があるのではないか、とも思いました。
とにかく災害時の協力支援体制は、常日頃の人間関係とも
関係があると思われ、家族が認知症であることを
ひた隠しにしている限り、適切な支援が得られない
と思います。
みんなに言って歩く必要はないけれど、信頼できる誰かを
身近に作っておくことが求められるのではないかと
思いました。
私の話のあとは、いつものように、高齢者・若年と
分かれるのではなく、地域ごとの小グループに分かれ、
話し合いが行われました。
私は「加古川市外」グループですが、その中の
ご家族は、やはり一般の避難場所で生活するのは
難しいと思うとお話されていました。
「福祉避難所」を確保すること。
それは本当に大切なことだと思いました。
結局、短い時間では結論は出せませんが、当事者や
支援者が声をあげて行かなければ改善はないでしょう。
備えあれば憂いなし
備えてあっても、本当に安全かどうかは分かりませんが、
備えておくことが少しでも被害を少なくすることに
繋がると思います。
2011年03月24日
たつの市の家族会に参加しました!

昨年から奇数月に開催されている、たつの市の
家族会にはじめて参加させていただきました。
今日は、第6回だそうです。
といっても、ご家族は5名(うち1名は最近
ご本人がお亡くなりになったそうです)
あとは社協職員1名、包括支援センターから2名、
医療ソーシャルワーカー1名、
認知症キャラバンメイト1名、認知症サポーター1名、
そして私。
現在、介護に悩まれている方4名に対し、8人の
支援者が集まったことになります。
贅沢だ~!
最初は「折り句」で頭の体操をしました。
「さくら」「はるのかぜ」を頭文字にして
俳句や短歌を考えます。
整いました!
(今日の昼ご飯)
ささにしき
くぎ煮を乗せて
らんちする
(春の高校野球を歌いました)
はれ舞台
るーるを守り
のびのびと
かん声あびて
ぜん力 投球
ま、こんな感じでございます。
その後、ご家族さんが互いに悩みを話したり、それについて
自分の経験を話したり、フリートーキング。
・入院期日が迫ってきたら、そのあとどうしたらいいのか
・嫁の自分にだけ介護の負担があって、情けない気持ちになる
・他地域に住んでいる家族は、口だけ出す(文句ばかり)が
何もしてくれない。
・徘徊の悩み。戸や扉に鍵をつける工夫
(これについては、ご本人がなぜ徘徊をするのか、という根本の問題を
解決しないと、鍵をかけて出られなくするというのは、見方によっては
軟禁状態ではないか?と思いましたが、だれからもコメントなし)
みなさん、悩みを語ってすっきりされたでしょうか・・・
次回は5月。来年度の初回になります。
実際、こんな集いがあることすら知らないご家族がいると
思うのですが、規模を大きくするつもりはないのかな~
市内のデイサービスに協力してもらい、ご家族に案内を届けて
もらうだけでも、救われる人がいるかもしれない。
そんなことを考えます。
2011年02月08日
男たちの介護

今日は、加古川の認知症家族の会の日ですが、
加古川・高砂の2市2町の地域ケア協議会との
コラボで、「家族介護者支援を考える
~介護する人/される人の関係性~」という
講演を聞きました。
講師は、立命館大学教授で、男性介護者と
支援者の全国ネットワークを運営(?)されている
津止正敏先生。
社会学的視点から、しかもとても熱い口調で
家族介護者、特に男性介護者のことを
語っていらっしゃいました。
介護という言葉がもつ暗くてつらいイメージを
ぬり替えようとされています。
男性介護者を「ケアメン」と呼ぼうと提案し、
家族の中で「嫁」が介護を担う時代が
終わったこと、これからの介護に求められる
支援、目指すべき社会のあり方を教えてください
ました。
先生が中心になって?「男性介護者と支援者の
全国ネットワーク」が今、全国展開しています。
http://dansei-kaigo.jp/
これから、たつの市の家族支援を考える時、
男性介護者の支援も別に考えないといけないなと
感じました。
とても勉強になった講演でした。
2011年01月11日
加古川元気会に行ってきました

[若年性認知症班で紹介されたエリザベス・マッキンレー著
『認知症のスピリチュアルケア こころのワークブック』]
今日は今年最初の家族会でした。
このブログの読者でコメントをくださった
みんみんさんをお誘いしての参加でした。
会の最初に、107歳の方がついたというお餅の
入ったお汁粉をいただき、そしていつもの
ように全員で歌を歌ってから会が始まりました。
若年性認知症を患っているMさんが前に立ち、
参加者のみなさんをリードしてくださいます。
そのあとはミニ講座。
今日は、グループホームで認知症ケアの
お仕事をされている方のお話。
認知症サポーターを養成するキャラバンメイト
でもあるそうです。
家族だけの介護には限界があり、地域で介護する
ことの重要性をおっしゃっていました。
家族が認知症であることをオープンにすること。
そこから支援が得られるというお話も。
これは信濃毎日新聞取材班の提言とも共通します。
今の世の中は「認知症」という「烙印」を押されてしまい、
個人が忘れさられてしまっている。
認知症になってしまってもできることがあるのだ。
できることを探し「生きていてよかった」と思える瞬間を
作ること。それが介護職の役割であるというお話も
されていました。
本当にそう思います。
そしてグループに分かれてのお話。
みなさん、それぞれのお正月を過ごされていた
ようですが、歌唱指導のMさん、年末にお孫さんが
生まれて、「孫」という歌を新しく覚えることを
され、とても意欲的なんだそうです。
今日もとても勉強になりました。
2011年01月07日
家族支援に向けて①

昨年のクリスマスイブの日、地域包括支援
センターの認知症担当の職員さんに市の
「認知症の人と家族の会」発足について話を
聞いていただきました。
そこで私が理解したことは、
・社会福祉協議会にできた「介護家族の会」は、
実は地域包括支援センターの依頼で再開され
(以前もあったが中断していた) 事実上、
市の「認知症の人と家族の会」の位置づけに
あること。
・よって、市民による会が発足した場合、
地域包括支援センターは協力や助言はしても
指揮をとったり、導いたりはしない。
2時間ほど話して、コトの進め方が違うのかな?
という印象を受けました。
私は、市におんぶに抱っこをするつもりはないけれど、
市は政策なり、実際困られている家族の情報が
あるはずで「それなら民間にはこういうものを
期待したい」という具体的な方向性を示してほしかった
のです。
仲間を集めるにしても、具体的なものがあって
初めて声かけができると私は思ったのですが、
そこをいつまでも議論しても仕方がないので、
私のほうが考えを改めました。
結論。
現時点で私のすべきことは、
・社協の「介護家族の会」を知ること
・「認知症者地域助け合い者養成講座」の修了生から
一緒に活動してもらえる仲間を探すこと
とうことで、「同窓会」の開催を呼び掛ける
ことになりました。
それをしてほしいなら、ズバリ言ってくれたら
いいのに、2時間もかけてそこに仕向けられた感が
あります。ま、いいけど・・・
そして、会場の手配が済み、案内文の添削を
していただいて、認知症者地域助け合い者養成講座を
修了した方々へ発送する運びとなりました。ふぅ。
あくまでも、私の決断でみなさんに呼び掛けるんで、
封筒も便せんも、印刷も、切手代も、会場代もみんな
自腹きりました!
いいんですよ。私がしたいことなんですから・・・
(と言いながら、ブログに書いてるけどね)
私は、行政には媚びません!
協働するには、対等な立場でと思っています!
では、投函してきます!
2010年12月14日
加古川元気会に行ってきました

今年最後の家族会でした。
先月、インドネシアの研修生を連れて
行ったので、皆さんから今日はいないのかと
聞かれました。
今日のミニ講座は、歯科衛生士さんによる
「口腔ケア」の説明。
口の中を清潔に保つことは、誤嚥性肺炎の
予防につながるということで、
歯磨きの重要性はさることながら、
昼間歯磨きできない環境ではお茶を
口に含ませること、それから舌の掃除も
した方がいいことなど教えていただきました。
しかし認知症が進行すると歯磨きすること
自体大変になることがあり、そのときの
工夫なども紹介がありました。
たとえば、
支障がない程度に歯磨き粉をつけ、
香りとともに歯磨きの仕方を思い出して
もらうとか、
認知症の方に歯ブラシを持っていただき、
介助者が別の歯ブラシで磨くと、自分が
磨いているように錯覚され、あまり抵抗が
ないとか、
歯磨きの技を習いました。
また、全員で舌を出したりひっこめたり
嚥下体操を。
そのあとは、いつものように若年性認知症の
班に参加して、ディスカッション。
今日は、新たに家族会の発足を予定している
地区の社協職員さんと地域包括支援センターの
職員さんが見学に来られていたので、皆で
自己紹介を。
来年、たつの市に家族会を作りたい!と
宣言したら、皆さんから拍手喝さいが(笑)
ご家族のメンタルケアの重要性や男性介護者の
ことなどが家族会の今後の課題であると
教えていただきました。
調子にのって帰りは、姫路のジュンク堂で
認知症の本、家族用の本などを買い込んで
しまいました(苦笑)
2010年12月10日
認知症の人と家族の会を!

今日は、介護支援専門員(ケアマネ)の
合格発表で、友人が合格しました!
おめでとう!
実は、彼女に代わってインターネットで
合否の確認をしたのは私。
自分が認知症ケア専門士に合格したような
錯覚に陥り、認知症の人と家族の会をたつの市に
発足させる妄想をしてみました(笑)
モデルは、加古川の家族会です。
平日の昼間。認知症のご本人がデイサービスに
行っている時間帯に開催。
場所は、はつらつセンターがいいかな?
季節のいいときは、脇坂屋敷も気持ちがいい
かもしれません。
加古川の家族会では、
①紹介
初回は全員自己紹介。
その後、新しく来た参加者のみ紹介
②今日の歌(1)
童謡などを歌う。
③ミニ講座
各種専門職が毎回ご家族の介護に役立つ
情報を話す。 約30分
④グループでの話
高齢者の介護か、若年の介護かで組に
別れ、楽しかったこと、悩みなどを
話す。テーマは具体的に決めていないが、
ファシリテーター(社協職員、介護施設職員など)
が進行役となり、なんとなくその日の
テーマが決まり、いろんな人が話をする。
⑤事務連絡
認知症の講座の紹介、テレビ番組の紹介など
⑥今日の歌(2)
童謡などを歌う。
そんな流れで、たっぷり2時間。
裏方の方は、名札の準備、資料のコピー、
お茶・お菓子の準備などをされています。
時々、認知症のご本人も参加されるので、
ボランティアなどがお相手をしたり。
会費は、1000円だったか、1200円だったか。
毎回ハガキでのご連絡も来ます。
毎回、30人ぐらい参加されているでしょうか?
月に1回の家族会。
加古川に比べたら私に力はないけれど、
家族会のもつチカラの大きさを知っている。
悩んでいるご家族の憩いの場として、
早く開催できたらいいな~と思います。
2010年10月12日
認知症家族の会に行ってきました

認知症を知るホームページ http://www.e-65.net/
早いものでもう前回からひと月たって
しまいました。
会場に到着すると、若年性認知症の班の方が
1Fのソファに座っておられ、「今日は
ご主人は?」と聞くと、今日は機嫌が悪い
とのこと。
ご主人はちょっと離れたところに一人で
立っていました。
よし!と思って「○○さん、こんにちは~」と
明るく挨拶。
自分をよく知っているような他人に会って、
よそいきの顔をしないはずはないだろう
そんな私のヨミは的中。
ご主人は、社交辞令かもしれないけど
微笑んでくださいました。
さ、行きましょう。
私たちは先に2階に上がってしまったけど、
きっと来てくれると思っていました。
それからしばらくはご機嫌で、何も分からない
とおっしゃりながらも、私も分からないんです
と言うと、安心したみたい。
今日の歌「赤とんぼ」のプリントが配布され、
それを眺め「あかとんぼ」と何度もつぶやいて、
平仮名で書いてある歌詞から読み始めていました。
そして最後はすべての歌詞を朗読。
とても脳を働かせているように見えます。
2枚目の「青い山脈」は文字数や漢字が多いせいか
「これは駄目だ」とおっしゃって、ひたすら
「赤とんぼ」の歌詞を読んでいました。
ただ開会時間が迫り、いろんな人がやって
部屋の雰囲気がガサガサしてくると落ち着きが
なくなって、「もういいだろう」と奥さんに
帰ることを促していました。
じゃ「赤とんぼ」の歌を歌ったら帰りましょう。
そうなだめながら、歌の時間になると、
上手に歌を歌われていました。
音楽の力は本当にすごいです。
講演が始まると、座っていることができず
部屋の中を歩き始められました。
奥さんも気にしながらも止めようとはしません。
しばらくして、私の後ろのほうで何かを
話していましたが、そのとき「トイレ」
という言葉を1回だけ話されました。
トイレに行きたいんだな。
そう思って、トイレに誘導。
2階はダメで、1階のトイレへ向かいました。
トイレに着くと自分で用を足されていました。
(利用者さんじゃないので、中までは
入りませんでしたが・・・)
その後、奥さんの存在を気にしつつ、でも
大きな声で話すでもなし、奥さんも会員の
方々とゆったりした時間が過ごせたようです。
今日の講演テーマは「バリデーション」
参考図書が紹介され、帰り道、本屋に寄ったついでに
購入しました。

2010年09月15日
認知症家族会に行ってきました!

昨日、感動的だったのは、若年性認知症を
発症された「お父さん」本人が来られたこと。
奥さんは、たぶん2回目の家族会の時、
初めて家族会に参加され、(今思うと)
かなり必死な状態で、介護に対する不安を
訴えておられました。
ここ何ヶ月か奥さんを通じて知る「お父さん」は
一体どんな方なんだろうと思っていました。
昨日はにこやかに登場され、知らない人が
大勢いることに一瞬戸惑った表情をされた
ものの、世間とは違う、温かな雰囲気、
自分が受け入れられていることを瞬時に
感じられ、ずっと穏やかに過ごされていました。
奥さんの表情も、初めて現われたときとは
全く違い、今では余裕さえ感じられます。
これが「家族会の力」
若年性認知症の班で話題になったことは、
まだまだ世間では認知症に対する「差別」が
あるということ。
認知症を患うことは、個人の汚点であるかの
ような扱われ方をしている。
世の中の偏見や差別をなくすことも支援者の
大切な役割だと感じました。




 地域ブログサイト
地域ブログサイト